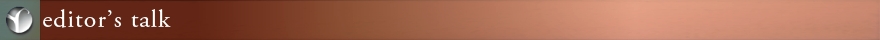books
『三島由紀夫の美学講座』 筑摩文庫

『金色の死』はあきらかに失敗である。
三島由紀夫は谷崎潤一郎の作品をそう断言する。
+
そしてこうも言う。
しかし天才の奇蹟は、失敗作にもまぎれもない天才の刻印が押され、むしろそのほうに作家の諸特質や、その後発展させられずに終わった重要な主題が発見されやすいことが多い。
三島は強く、傍点をもって谷崎潤一郎の『金色の死』を引用する。
そのうちでも最も美しいのは人間の肉体だ。思想と云うものはいかに立派でも見て感ずるものではない。
三島は、肉体、つまり見た目が思想よりも立派だというところに同意しているのだ。『金色の死』の前半の岡村は、文芸をこなしつつも肉体の方が美しいと主張している。そこが良いと。そして後半でそれを否定しているところが駄目だと言っている。
鉄棒の方が、却て鞭のような彼の体でぴたりぴたりとさも痛そうに打たれました。岡村君の、肌理の細かい白い両脛には、無数の銀砂が薄い靴下を履いたように付着して居ました。
これは『金色の死』の中で、三島が敢えて引用しなかった岡村君の美しい肉体への賛辞の部分。文章的にも内容的にも三島好みである。
三島由紀夫が封印されていた『黄金の死』を全集に取上げ、長い解説文を書いた理由は、このあたりにありそうだ。三島は、文学的資質を充分にもちながら器械体操を優位とする岡村が、(その状態を三島はよしとする)最後には金に飽かせて西洋美術の模倣品の理想郷を作った、そこが駄目だと言っている。どうして前半のままの岡村で、そしてそのままに死なないのかと思っているに違いない。
『黄金の死』は三島由紀夫の生き方に大きな影響を与えたように思える。そして作品にも。
++
三島は書く。
それにしても『金色の死』の、美の理想郷の描写に入ると、とたんにこの小説は時代的制約にとらわれたものになる。統一的様式を失った日本文化の醜さを露呈する。
たしかにそれはそうかもしれない。しかし『金色の死』のラストを三島の非難からかばいたくなる誘惑にかられる。まぁ良いではないか。そのばらばら度合いも良しと。
谷崎潤一郎は、理想郷に入れるべき美術をまず日本は豊国と西欧はロートレックを上げている。三島がそれを苦笑している…しかし隔たった山の一角の、白亜の洋館の廊下(ベランダ)を…と『金色の死』の、谷崎の書く理想郷と、非常に近しい白亜のベランダ付きの洋館に、ロココを配して三島由紀夫は住んだのではなかったか。
まさに三島由紀夫は魅入られるように『黄金の死』を生きたのだ。
+++
谷崎の描いた、金粉を塗りたくってパフォーマンスをし、皮膚呼吸ができなくなって死ぬというのも理想の庭園に相応しい。谷崎潤一郎は『金色の死』で耽美世界に足を少し踏み込んでいたのだ。この時代に言われていた耽美ではなく、西欧にあるような本格的な耽美に。踏み込んでしまったと思ったのか、そのあたりは分らない。
三島由紀夫の嘆美は、谷崎の耽美とも少し異っている。どっちをとるかと言えば、耽美に関しては、谷崎をとりたい。谷崎潤一郎の理想郷の美術の中には、若冲が入っている。『金色の死』が1914(大正14)年に書かれたことを思うと、谷崎は何かをつかんでいたように思う。谷崎の耽美の嚆矢として、僕は谷崎世界をレスペクトしたい。
++++
三島由紀夫の思う通りの美的価値観で終わらず、しかも作品自体を葬ったことに対して三島由紀夫は抗議しているように見える。谷崎潤一郎が貫かなかった[器械体操が思想を凌駕する]という思想を補完するかのように三島由紀夫は人生を生きたのだ。
三島のデカダンスは、行為の耽美者である。妄想と模造の思想のために死を賭してしまう三島由紀夫は、そのことで最高の耽美者と言えるだろう。本物ゆえに死を賭すのは殉死である。三島は文学者として生き、文学者として死んでいるのだ。虚構を最高の模造品にして、理想郷にして、かなうはずのない主張を掲げて、毎日していたような切腹遊戯のようにしてセクシャルな耽美を現実に一瞬持ち込んで死んだのだ。
ただ三島由紀夫がその模造性をどのように意識化しえていたのかは、これも分らないところである。意識しないからこそなりえたとも言えるし、興味深いところだ。
update2008/04/20