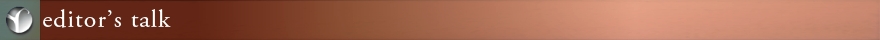stages
「こんなに愛しあったのに」 指輪ホテル
学生で言うと夏休みの期間中、指輪ホテルは、ずっと海で稽古をしながら作品を作り続けていた。切れ切れに伝わってくる稽古風景、それは鎌倉の海岸だったり……。夏の終わり、瀬戸内国際芸術祭の最後の三日に「こんなに愛しあったのに」が上演される。電車を乗り継いで、船に乗って、会場にたどり着いた。
ビーチに寝そべって英語の地理学の本を読む女、たき火をしてご飯を作る女…。始まる前から始まっている。試しに手を振ってみると、手を振り返してくれる。直島の宮ノ浦海水浴場、海の上に電話ボックスが浮かんでいる。その向こうに夕陽が沈んでいく。上演開始だ。颱風の雨が予想されている。大丈夫か。指輪ホテル。
電話がリーンと鳴り、一人の女が自転車で浜辺に乗りつける。横倒しに放置して、ブーツを投げ捨て、服のまま沖に泳ぎ出す羊屋白玉。電話ボックスに泳ぎ着いた女は、受話器を取る。
「え? どこから電話しているの…」
羊屋さんの電話は、冥界電話と思っている。パラボリカ・ビスの「断食芸人」でも、死んだはずの断食芸人と電話で話していた。時空をもつなぐ。死者とも話せる、どこにでもつながる。電話の相手は、生きているのか死んでいるのか分からない。だいたい羊屋さん自体が最後まで、生き死にが分からない。
登場人物は女だけ、乙女たちの夏休み。そんなイメージが浮かぶが、それは、始まる前の印象。本編は、かなり深みのある女たちの話。葬式を途中で抜けてきた女、結婚式を抜けてきた女、生まれたばかりの赤ちゃんなのに大きく育っている女、普通には他人から見えない女…。一人が死に/海に飛び込むと、誰かが産まれる……どういう構造になっているのだろう。
海の野外劇であり、島の演劇でありそして女たちの演劇、そして死者たちの演劇でもある。愛しあった人が、居なくなった時、それは恋人同士だったり、親子だったり…、残された女はどういう風に生きるのか。死者が生きているかのように共に生きるのか…。夏の間、浜辺で暮らした島の女たち、この島の女も、他から来た女も、みんな島の女として生きたこの夏。
死んだら甕に葬る、そうすると長い時間かかって水になるというような民族学的伝承譚が自在に組み込まれて、女たちの話は、哀しいけれど島の自然に戻っていくことで、大らかさをもっているような拡がりをもつ。
だけど島は闇を抱えている。直島には三菱マテリアルがあって、精錬で公害を垂れ流した。島は禿げ山になった。犬島も同じだ。植林しても木は大きく育たない。豊島には違法の産廃が残されている。燃やすのは直島だ。でも奇麗になったはずの黒い砂を誰も使わない。だから直島は黒い砂で埋もれていく。そんなことも密かに織り込まれている女たちの夏。
update2013/09/12