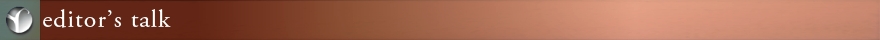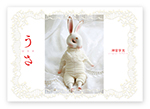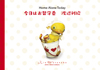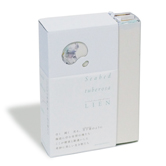stages
『失われた時間を求めて』 阿佐谷スパイダース

『ドラクル』の時の作・演出の長塚圭史は一体、何だったんだ?
海老蔵の我が侭に負けた? それともあれが本来の力?
阿佐ヶ谷スパイダースは、作・演出、そして俳優もつとめる長塚圭史が中心の3人のメンバーで構成された演劇ユニット。その度ごとに役者をプロデュースしてくる。日本の劇団は、どちらかそいうと家族制度のようなところがある。お父さんが作・演出。お母さんが看板女優。喧嘩したら劇団ごと解散になる。他のメンバーはたまったもんじゃない。
『失われた時間を求めて』は、一つのベンチと、それが置かれているどこだか分らない場所、そして不可解な話をし、行動をする人たちの台詞によって成立している。
ずいぶん前にいなくなった猫を探し続ける人、その行動を探って手伝おうとする女性…。猫を探す人の兄弟もでてくる。人を殺したいというネガティブな妄想を抱き続けている男は、落葉を拾ったりばらまいたりナイフを振りかざしたりする。
この演劇は「動物園物語」(エドワード・オルビー作)の設定を使っている。もしかしたら「失われた時を求めて」(マルセル・プースト)のテーマも使われているかもしれない。
設定をパクるというのは、大正時代から現在まで平気で行われているが、いかがなもんか。
それでも『失われた時間を求めて』は面白かった。前衛の匂いすらしなくなった日本で、これは前衛の部類に属する。
記憶と時間と空間というものは、人間の主観によって大きく異るものだ。時代や社会の状況によっても異る。そのずれを描くことで社会格差などを鮮やかに浮かび上がらせるのが、「動物園物語」や「失われた時を求めて」だった。
その設定を現代の日本に置き換えるとどうなのか? というのが長塚圭史の今回の実験ではないだろうか。格差は大きくなり、表の顔と裏の気持は遊離しているにも係わらず、非常に平板に見える姿をしている今の人たち(それは年配者を含めてのこと)が、意識下の最も気になっていることがらによってコミュニケーションするとどうなるか? 実験に答えはない。結末もない。
それでもよいのは、実験の果てに見えてくるものが、かみ合わないままどこにも到達しない関係だからだ。それは、今の現状を見事に反映している。
この演劇を不条理と言うのは簡単だ。でもそうじゃない。不条理にすらなれない、やりきれないさ、だらっとかみ合わないどうしようもなさだ。失われた時間は永遠に失われ、回復の兆しすらない。やり切れなさの向こうにあるのは何だ。
僕の脳裏には白い絶望という言葉が浮かぶ。
update2008/05/18