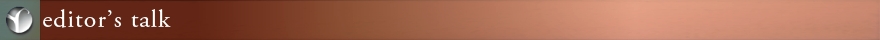stages
奇ッ怪其ノ参[遠野物語]前川知大・作・演出
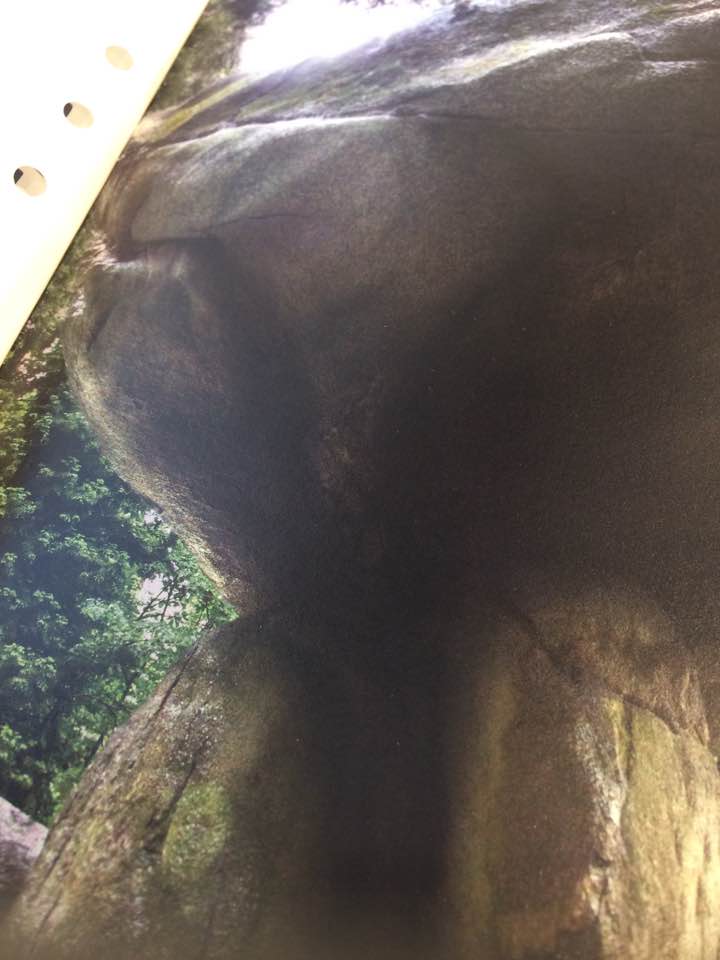
奇ッ怪其ノ参[遠野物語]前川知大・作・演出
蜷川幸雄追悼の「ビニールの城」の暗澹たる出来の悪さに、所謂商業演劇の未来の暗さを予感してしまう、その嫌な感じを、払拭してくれたのが、前川知大・作・演出の「遠野物語」だった。
社会の合理化を目指す「標準化政策」に違反した疑いで、ヤナギダ(仲村トオル)が逮捕され、イノウエ(山内圭哉)が審査のために呼ばれるという設定だ。前川知大は、設定が巧い。設定をした後で、世界観を引っぱり込んで舞台を作っていく。そこが意識的に設計されているように思う。いいな。
イノウエは井上円了、ヤナギダは柳田国男だ。前川の戯曲では、合理と科学で怪しいものを説明しようとするイノウエと怪しいものこそ伝えるべきもので、存在すべきものだとするヤナギダとの対立になっている。これは「真景累ヶ淵」の真景が神経から来ている、怪しいものを人間の頭が生みだした妄想とする動きがあったことに重ねられる。
近代文学は発生の時から怪奇と幻想を孕んでいたように思う。幸田露伴の「対髑髏」などを読むとこれが過渡期と創成なんだとわくわくする。その系譜に泉鏡花も柳田国男もいる。鏡花は流行っているがそのトリビュートを見ると、そうか?と思うようなものが多くパターン的認識が多すぎる。
話は飛んでいくが、先日武蔵美で山本直彰に呼ばれて講義をしたが、反応で驚いたのは、類型化、分類化、典型化して俯瞰する切り口を望まれていたことだ。典型なんてこれから新しい芸術を作る美大生にもっとも不必要なものなんじゃないか。僕はむっとして普遍的なことを教えているんですかと教授に聞いてみたりした。外れて外れて、それでも出てくるものが芸術に必要な普遍ではないのか。まぁいいや。
だから前川の「標準化政策」にはぎくりとして腑に落ちるというか共感を覚えた。作・演出の前川知大は、架空の日本に「標準化政策」が施行されているという設定で奇ッ怪其ノ参「遠野物語」を構成している。「標準化政策」とは、全てに「標準」が設定され、物事は真と偽、事実と迷信に明確に分けられ、その間の曖昧な領域を排除するというものだ。この[設定]が、前川知大の演劇の根幹だ。
おそらく前川は遠野に取材してその余りの何もなさに、[標準]が幻想を壊した(これは僕の言い方だけど)と思ったのだろう。幻想文学が衰退して「夜想」が困っていることと、標準だの典型だのに押し切られている今の表現教育とが実は密接しているんだと、奇ッ怪其ノ参「遠野物語」を観て衝撃を受けた。で、なんかかなりめげてしまった。ずっと考えたりやってきてどうにもならないのが教育の部分だから。武蔵美の講義の後、学生と教授との会話に耐えきれず尻尾を巻いて逃げ帰った僕に、未来は昏い。
update2016/11/07
stages
押絵と旅する男
押絵を旅する男/江戸川乱歩
朗読 井上弘久 美術 日野まき

乱歩と潤一郎の版権が今年切れる。青空文庫では一斉に解禁になるだろうし、一方、詳細な研究の進んだ谷崎潤一郎の全集の刊行も進行している。
そんなこともあってか、ないのか、茶会記で乱歩の朗読会を企画することになった。茶会記は四谷にある喫茶バーでイベントもする。
茶会記は羨ましいほどに言い名前だ。
作を選ばせてもらうなら、「押絵と旅する男」。自分としてはこれ。人形繋がりということもある。夜想の「カフカのよみ方」で体得した本のよみ方その一。自分の得意ジャンルからの視点で入る。
僕で言えば、踊りとか人形とか。他の人のカットインに乗るという方法もある。贅沢な感じで髙橋悠治のピアノを弾く指とか。もちろんピアノや音楽に素人な自分では、乗り切れないけれど、目の前が開けるような視点をもらえることもある。
押絵を旅する男 Ⅱ
2月13日、14日にパラボリカ・ビスで再演するのだけれど、日野まきの美術が朗読をブローアップしている。乱歩の「押絵と旅する男」の挿絵でもあり、井上弘久の朗読演劇の美術でもある。
挿絵といえば、小村雪岱。「一本刀土俵入」の取手の宿の舞台装置の鏝絵で六代目菊五郎を喜ばせ、台詞が美術作品に及んでいる。昔のコラボレーションは粋に満ちあふれている。自分を主張するのではなく、コラボレーションして出きあがるものに対して情熱をかけているのが素敵だ。
ともあれ人形で「押絵を旅する男」を読むと兄さんと弟の感情の交錯が見て取れて面白い。視点をどこに置くかで隠れているものがでてくる。
「押絵と旅する男」は、乱歩の覗き見趣向、レンズ嗜好がからくり箱にしっかりと嵌まった名作だけれど、今回、朗読を手伝っていて気がついたのは、「ピントがあう瞬間」の魅力だ。
押絵を旅する男 Ⅲ
乱歩は、中学生の頃、部屋に閉じこもりっきりになって雨戸の節穴から差し込む光を見ていたことあがあり、それを自分では憂鬱症と言っていた。差し込んだ光が天井にもやもやを作り、それに驚愕して慄いていたがしばらくしてその正体を発見する。(「レンズ嗜好症」)
何だか分からないものにピントがあって像がくっきりする。その瞬間のゾクゾク感、それが乱歩のレンズ嗜好なのだ。「押絵を旅する男」は、態々魚津へ蜃気楼を見に出掛けた帰り途であった。私によって書かれているが、相変らずの癖というか文体で、これは乱歩自身のことである。不用意に小説の中に出てくる乱歩のその有り様を愛でる中井英夫が分かるようになったのも、今回の大きな収穫であるが、それはともあれ、蜃気楼、遠眼鏡のピントが合う瞬間の魅力が乱歩の囚われていた書くことの魅力の一つだろう。押絵がなんだったというユリイカの瞬間とその設定が、乱歩の書く醍醐味だったのではないだろうか。
update2016/01/24
stages
第二の秋 シュルツ 勅使川原三郎
第二の秋/シュルツ 勅使川原三郎 Ⅰ
父によれば、これは気候のある種の中毒症状であって、その毒は私たちの美術館に所狭しと置かれている爛熟退化したバロック美術に発するのである。
長すぎる秋を苦しめる美しいマラリア熱、多彩な妄想の原因となる。美とは病なのだ____と父は教えた____美は秘密の感染による一種の震えであり、腐敗の暗い予兆である、(シュルツ「第二の秋」工藤幸雄訳)
シュルツの「第二の秋」は頽廃に充ち、さらにぎりぎりの絶望を孕んで、爛熟した果実のようだ。その「第二の秋」を勅使川原三郎が、舞台化した。「春」「ドド」を原作にしたシュルツ・前二作とは、少し演出を変えている。「第二の秋」に入って、かなりその外へ飛翔している。大劇場にふさわしい抜けるような秋の空気感が拡がる。
シアターχで踊ったシュルツ原作の「春」「ドド」を見たときに、思ったのだが、ある種のダンサーや演出家とか、舞台の上に乗る人たちは、小説を読むときに、人物に入り込んで、小説の風景の中を生きるようにして読むのではないかと。もちろん私たちも、主人公に気持ちを投影して読むというのはあるが、さらに主人公になって、小説の中であたりを見回したり、もしここで風が吹いてきたら、こんな風に感じたり動くだろうなというようなことまで分かってしまうような、読み方。
勅使川原三郎は、「春」を「春、一夜にして」「ドド」を「ドドと気違いたち」というタイトルに変えたが、一夜にして、気違いたちというところが、作品からでて作品の延長として、描いたところだと思う。両作品とも、短編が朗読され、その朗読を音楽として踊っていく。踊りと合わせて聞いていると、勅使川原三郎がどうシュルツを読んでいるのか、そしてどうそこから出てイマジネーションを拡げているのか、リアルに伝わってくる。
この2作品で勅使川原三郎の、これからの覚悟が伝わってくる。どう踊るのか、どうそこに居るのか/あるのかということをより優先使用としている。大きな劇場公演では、見せる要素、ドラマッティックに盛り上げる要素が、踊るということに付加される。勅使川原三郎は、視覚的演出にも特異な才能をもっている。(どこかで歪んだパースペクティブとか……)それを極力抑えて、踊るということに、晒しても踊るということに特化していたのが、シアターχでの2作だった。
一転して、東京芸術劇場での「第二の秋」は、作品から出て自由に踊る部分が多く、演出も従来のようなエッジのたった、光を駆使した演出も入った舞台だった。大劇場は、このままに世界に招聘される演出と躍りで続けていくのだろうが、おそらく、自ら作った劇場と小規模な劇場では、踊る身体を変容させながら変化を続けていく踊りを選んだのではないだろうか。
update2013/09/16
stages
「こんなに愛しあったのに」 指輪ホテル
学生で言うと夏休みの期間中、指輪ホテルは、ずっと海で稽古をしながら作品を作り続けていた。切れ切れに伝わってくる稽古風景、それは鎌倉の海岸だったり……。夏の終わり、瀬戸内国際芸術祭の最後の三日に「こんなに愛しあったのに」が上演される。電車を乗り継いで、船に乗って、会場にたどり着いた。
ビーチに寝そべって英語の地理学の本を読む女、たき火をしてご飯を作る女…。始まる前から始まっている。試しに手を振ってみると、手を振り返してくれる。直島の宮ノ浦海水浴場、海の上に電話ボックスが浮かんでいる。その向こうに夕陽が沈んでいく。上演開始だ。颱風の雨が予想されている。大丈夫か。指輪ホテル。
電話がリーンと鳴り、一人の女が自転車で浜辺に乗りつける。横倒しに放置して、ブーツを投げ捨て、服のまま沖に泳ぎ出す羊屋白玉。電話ボックスに泳ぎ着いた女は、受話器を取る。
「え? どこから電話しているの…」
羊屋さんの電話は、冥界電話と思っている。パラボリカ・ビスの「断食芸人」でも、死んだはずの断食芸人と電話で話していた。時空をもつなぐ。死者とも話せる、どこにでもつながる。電話の相手は、生きているのか死んでいるのか分からない。だいたい羊屋さん自体が最後まで、生き死にが分からない。
登場人物は女だけ、乙女たちの夏休み。そんなイメージが浮かぶが、それは、始まる前の印象。本編は、かなり深みのある女たちの話。葬式を途中で抜けてきた女、結婚式を抜けてきた女、生まれたばかりの赤ちゃんなのに大きく育っている女、普通には他人から見えない女…。一人が死に/海に飛び込むと、誰かが産まれる……どういう構造になっているのだろう。
海の野外劇であり、島の演劇でありそして女たちの演劇、そして死者たちの演劇でもある。愛しあった人が、居なくなった時、それは恋人同士だったり、親子だったり…、残された女はどういう風に生きるのか。死者が生きているかのように共に生きるのか…。夏の間、浜辺で暮らした島の女たち、この島の女も、他から来た女も、みんな島の女として生きたこの夏。
死んだら甕に葬る、そうすると長い時間かかって水になるというような民族学的伝承譚が自在に組み込まれて、女たちの話は、哀しいけれど島の自然に戻っていくことで、大らかさをもっているような拡がりをもつ。
だけど島は闇を抱えている。直島には三菱マテリアルがあって、精錬で公害を垂れ流した。島は禿げ山になった。犬島も同じだ。植林しても木は大きく育たない。豊島には違法の産廃が残されている。燃やすのは直島だ。でも奇麗になったはずの黒い砂を誰も使わない。だから直島は黒い砂で埋もれていく。そんなことも密かに織り込まれている女たちの夏。
update2013/09/12
stages
『地下室の手記』 イキウメ/カタルシツ
『地下室の手記』の手記
Ⅰ
劇団イキウメは、本公演からはみだすような企画を「カタルシツ」という名称で上演しはじめた。やりたいことを実験的にやる。そんな静かな気合いが伝わってくる。
カタルシツは、「語る」と「室」をカタルシスに引っかけた造語だろう。
やろうとしていることは、朗読ということも関係しているのかもしれない。
パラボリカ・ビスで上演した、指輪ホテルの「断食芸人」(カフカ)の朗読も、不思議な形態をしていた。
朗読はまだまだ開発の余地がある。というか、朗読で実験をする、そんな気分なんだろうな。
シアターカイで勅使川原三郎が踊ったシュルツも、全面、朗読が流れている中だった。
++
さて「カタルシツ」の第一段は、ドストエフスキーの「地下室の手記」。
「地下室の手記」は、地下室に籠ってひたすら社会や友人、自分の周りのあらゆるものに恨み辛みを言い募る自己愛の男のモノローグである。ドストエフスキーが、「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」へ移行する端境期に書かれた、とてつもない暗さと呪詛のようなネガティブさに溢れた異色の作品と言われている。前川知大が現代に置き換えて上演した。
登場人物は、親の遺産で働かなくてすむようになった40歳男(安井順平)と、娼婦( )の二人。
話すなら自分一人についてだけ、地下室のお前のみじめさについてだけにしてくれ。〈俺たち皆〉などと言ってもらいたくないね」
これは原作の部分。ニコ動の画面を流れるような、突っ込みを自分に入れている。どれだけ現代の、今の、日本的なんだろうか。
そう前川知大は、地下室からニコ動らしきサイトでいるかいないか分からない相手に向かって、語りかけるという設定
で、「地下室の手記」をはじめる。かなり置き換えをしているかのような印象を与えるが、実は、かなり原作にはかなり忠実だ。「地下室の手記」の二章がほぼ丸ごと使われている。一章は哲学的や思想的、自分の身上が書かれていて、それは上手に今に変えられている。
今の現実感から、場面ごとにぐいぐいと虚構世界に入っていくという、前川知大の真骨頂はここでも活きていて、いつのまにかドストエフスキーの世界に入り込まされているのだが、それとは気づかせない。凄いな。このテクニックは。
この違和感のなさは、どこからくるのだろう。
前川知大が以前に読んだとき、自分のことではないかと思ったと、書いているくらいだから、元々、自分のものになっているのだろうが、こういう自己愛の男、今ならどこにでもいるよな。自己愛の強い落ちこぼれ官吏は、おそらく何パーセントかは、帝政ロシアの時代と社会が生み出したのだろうから、それを思うと、今の日本は、あの時代と同じくらい人を暗くする、圧迫感があるのかもしれない。
それにしても、たくさんいるよな。こういう男。
update2013/08/22
stages
平成中村座
染五郎が…。
猿之助さんは、自分で歩くと言いながら、仲見世の入り口までもたどり着けなかった。かつて自分の動きが鈍くなったらもう舞台に出ずに演出に廻る、それをちゃんと言ってくれる人を側に置きたいと宣言していたが、そうはならないのが歌舞伎で、あんな歳にまでなって女形をやるなんて、私は絶対に自分にそれを許さないと公言しながら、やはり歳をとっても舞台にあがるものだ。老いに至ったときの過ごし方は、それはそれで興味があって、妄執というのも良いし、あっさりと後進に譲るのも良い。猿之助さんは、襲名披露で舞台で演じたいという思いを強くしている。
澤瀉屋がお練りをしているその頃、浅草寺の脇を抜け、浅草神社を通って江戸通り、浅草六丁目、聖天様、山谷掘り…と歩けば、平成中村座に着く。ちょうど、出し物は、勘九郎と染五郎の「三社祭七百年記念・四変化・弥生の花浅草祭」。若手のスピードを十分に活かした振付は、さすが、藤間勘十郎。当代、すべてのジャンルの振付師の中でも僕の大好きな人。踊り手の身体の特質に合わせて振付けるのが好き。
染五郎の踊りをそんなに気にしていなかったけれど、ある時、ちょっとした踊りでふっといいなぁと心を惹かれる時があって、見るようになったが、それはいつも勘十郎の振付けだった。それから勘十郎振付けかどうか見るようになったが、染五郎との組み合わせは相性抜群のような気がする。勘九郎、染五郎、勘十郎振付けで、それを目的に昼の部に駆けつけた。期待通り。二人の息があったデュエットは、素晴らしかった。このスピードは今でしか実現できないだろうし、勘九郎の良さも十分に引き出していた。
平成中村座、今回は7ヶ月間、浅草で興業をした。病明けの中村勘三郎、終始真面目に舞台をつとめていて、それゆえにどこか本調子でないように思えた。しかし勘三郎ただでは起きない。座頭としての力量をいかんなく発揮して、自分の出番を控えめに、若手の育成や実験を繰り返していた。菊之助を立役として起用し、声を嗄らして熱演する真面目さに、カーテンコールで、良くやったと舞台上で褒める粋さはたまらない。いよぉ座長と声をかけたくなる。
菊五郎は劇団のヘッドとして素晴らしいが、勘三郎は、かつて浅草にあった江戸三座・中村座の座主、中村勘三郎の名を継ぐ役者だけあって、劇場主としての力量ももっている。菊五郎や猿之助が劇団制を活用しているのに比べ、勘三郎は劇団よりむしろ座の元に集まる個性の組み合わせに興味をもっているように思われる。菊五郎さんはむしろさっぱりとしている人で老醜とは縁ない。(今のところ…)先代松緑が、二月堂のお水取りに取材して舞台化した、『韃靼』も菊五郎さんの隠れ十八番だったのに、あっさりと松緑さんに譲ってしまって自分は出演もしない。千代の富士にすべてを譲った北の富士のようだ。共通は、粋な遊び人ということか…。
勘三郎さんが『め組の喧嘩』初役とは知らなかった。それにご祝儀を出したのか、團十郎さんの体調を気づかってのことなのか、今月は、関西で團菊祭が催されているのに、劇団の立廻りメンバーが「め組」に総出演してる。しかも菊十郎、橘太郎という劇団の看板立師二人が、腕をふるっている。「め組」をやるならうちのわけぇもんがいるだろう、もってきな……ということなんだろうか。真相は分からない。立廻りは勘三郎さんのところの立師に気を使ってか、今一つだったが、久しぶりに菊十郎さんの鰹売りを見れたし、橘太郎の絶品、白須賀六郎が見れたし、さすがに勘三郎さんの役者配置は素敵なものがある。
菊五郎さんは菊之助さんにおそらく立役を教えていないだろうから、それを経験させようとした勘三郎さんということもあるし、同じように勘三郎さんは新勘九郎に、自分を追ってこいとは言っていないような気がする。むしろ新しい勘九郎を作れと命じているようにも思う。この7ヶ月の勘九郎は、予想以上にしっかりと床を踏んで演技をしている。古風な歌舞伎の時代の錦絵に出てくるような、荒事が似合うような、そんな風をしている。菊五郎劇団で武者修行する勘九郎というのを見たい気もする。実現したらいいなぁと思いながら、僕の平成座は幕を閉じた。
update2012/06/04
stages
『誰も知らない貴方の部屋』@はこぶね 庭劇団ペニノ
『誰も知らない貴方の部屋』

押し入れの中、拡がる妄想の部屋。
子供の頃、押し入れの中に寝るのが好きだった。天井の板がすぐ目の前にあり、眠りに落ちながら宇宙を翔ぶ自分を夢想した。タニノクロウの押し入れの妄想は、そこにまた小さな部屋を創造しそこから世界を覗くという二重の押し入れ部屋で展開する。
それにしても…とふと思う。子供の頃はあんなに狭い場所が好きだったのに、今は閉所恐怖症になっている。寺山修司の天井桟敷の完全暗転は大好きだけれど、係わっていたから構造を知っていたので辛うじて耐えられた。燐光群の「トーキョー裁判1999 ACT1〈解体〉ACT2〈航海〉」では、観客が船体の乗客として閉じこめられる設定にパニックに陥りそうだった。
タニノクロウの密室感は天井桟敷や燐光群の演劇独特の密室性、観客を追い込むような仕掛けと対極にあり、治療のために箱庭を眺めているような、ほんわかとした不気味さがあって、心がリラックスする。
庭劇団ペニノという名の通り、箱庭のような小さな舞台でタニノクロウ世界は、真骨頂を発揮する。『苛々する大人の絵本』の続編になっている『誰も知らない貴方の部屋』は、続編と言っても特に繋がりがあるわけでもなく、元自分が住んでいたマンションを改造して劇場にしているということと、その狭い空間がさらに上下に区切られていることと、シチュエーションや道具が似ているということで、きっとタニノクロウの妄想の一つが、あるいは見た夢が展開されているのだろうと思う。
上の階では、修道女のような服を着た、羊の精が「わたし、サボテン屋さんになろうかなぁ」ってぽそりと言う。…「ま、サボテン屋さんは難しいか…」などと独り言のような会話をしながら舞台は始まる。小さな窓の向こうには森が見えて雪が降っている。まさに箱庭…下の階(もしかしたら地下室?)にはオタクな兄弟が住んでいる。「兄さんの顔を作ったよ、誕生日に…」床には兄さん役の俳優そっくりの被り物がいくつも置いてある。そこに兄さんが入ってくる、部屋が狭くて弟とプロレスをするように絡み合う…そんな風に、摩訶不思議な世界が展開する。
演劇に社会批判性とか、前時代の演劇スタイルへのカウンターとかを含まなければならないという呪縛から完全に逸脱しているタニノクロウの妄想世界に孤立感はない。もしかしたら、無意識の深いところで共通にもっている物語の原型にたどりついているのかもしれない。そうだとしたらこれは平成のシュルレアリスムというような演劇なのかもしれない。
update2012/03/06